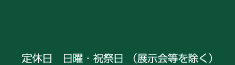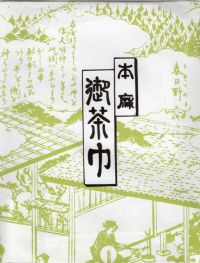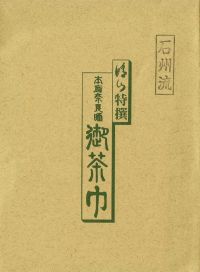※日時指定、コレクト指定のない小型商品はお得になります。
振り込みを選択され、日時のご指定のない場合で商品が小形、軽量、薄型、少量の商品に関してレターパックライト、レターパックプラスにて発送が可能です。
送料がそれぞれ、全国一律、570円(プラス)となりお得です。
(※内容量、大きさには限度があります。超える場合は通常の送料となります。)
通常のお申し込みを下さり、上記の条件に適う場合、確認メールにこちらから
改めて、金額をお知らせ致します。
当社からの確認メールをご確認の上料金をお振り込み下さるとお得です。
※対象商品例
お抹茶(40g缶4個程度、100g缶2個程度)茶巾、書籍(A4サイズまで)
灰(2個程度まで)お香 懐紙、など。
こわれものは送れません。
② 「茶巾」=清潔を旨として、茶事、茶会などには新しい物を用います。
流儀により麻の織り方や寸法が異なりますので注意しましょう。
《おすすめはこちら》
茶湯・晴山おすすめ、奈良晒本麻茶巾
この茶巾は正倉院御物にある奈良晒と全く同じ原料及び手法(手紡・手織)で製作されたものです。古来・茶巾に奈良晒が使用されてきたのは茶祖、珠光が優れた吸水性に着目したものと思われます。
現在も江戸中期(文化・文致時代)と同様の、糸車・織機が使用されて、当時の技法を用いて、一本づつ糸をつないで手作りしたものです。
茶湯・晴山がお薦めします。
石州流・江戸千家 用
石州流と江戸千家では「保田織(ほたおり)」と呼ばれる特別な織り方をした奈良晒しを用います。
サイズは表・裏千家と同じですが、流儀にあったものを使うことおすすめします。
奈良晒保田織 本麻茶巾
茶湯・晴山がお薦めします。
奈良晒保田織 本麻手巾(水次用)
水次に用いる大きめの茶巾です。
茶湯・晴山の手巾は最上級保田晒を使用しています。
宗徧流
宗徧流でも「保田織」の茶巾を使いますが、他流より細身の物を用います。
奈良晒保田織 本麻茶巾
茶湯・晴山がお薦めします。